「太宰、よくわからなかった…」
それ、あなただけじゃありません。
太宰治の小説って、文章はやさしいのに、読後に残るのは“ふわっとした違和感”。
感動よりも、どこか置いてけぼりにされたような気持ち──。
「暗い」「意味不明」「面白くない」なんて声も、よく聞きます。
実際、年間200冊以上読む私も、太宰だけは「え、これどう受け止めれば?」と悩むことが多くて(笑)
でも最近、その“わかりにくさ”にはちゃんと理由があると気づきました。
短編をいくつか読み比べてみると、無駄が一切なく、
皮肉やユーモアを効かせた、精巧な構成の小説だとわかります。
親しみやすいのに、じつは緻密。
共感を誘いながらも、どこか冷めた視線がある。
そのギャップこそが、太宰が“文豪”と呼ばれる理由なのです。
今回は短編『灯籠』を入り口に、
「太宰作品がなぜ読みにくいのか?」を、3つの視点からやさしく紐解いてみます。
太宰の小説がわかりにくい3つの理由
大きく分けて、次の3つの理由が考えられます。
① 「物語らない」から

太宰の短編には、物語としての起承転結や明確なオチがありません。
「何が起きたか」よりも、「そのときどう感じたか」に焦点を当てた作品が多いのです。
たとえば『女生徒』では、一人の少女の一日が淡々と綴られるだけ。
事件も展開もないまま、読者は彼女の細やかな感情の波を追っていきます。
これは、太宰が“心情のスナップショット”に重きを置いているから。
ストーリーではなく、感情のかけらを静かに差し出してくるので、
「この小説は何を伝えたかったのか?」
という問いにすぐ答えを出せないのです。
② 「語られないこと」に真実がある
太宰の登場人物は、本音を語りません。
ときに嘘をつき、演じ、皮肉や自虐で自分を覆います。
つまり、「この登場人物の言っていること=本心」とは限らないのです。
たとえば短編『灯籠』では、少女・さき子が青年・水野と出会い、彼が水着を持っていないと知ると、町の商店で水着を盗んでしまいます。
なぜそんな突飛な行動に出るのか?
作中では、さき子の心理はほとんど語られません。
恋心? 衝動? それとも、日常からの逃避?
読者にその「行間を読む力」が求められます。
太宰の作品は、“説明”のないところにこそ、心の核心があるのです。
③ 時代背景・価値観のズレ
太宰の作品には、昭和初期(戦前〜戦中)の社会や価値観が色濃く反映されています。
たとえば『灯籠』で、さき子は水野との関係が周囲に知られたことで「男狂い」と陰口をたたかれます。
たった一度の淡い恋、それだけで“ふしだら”と決めつけられてしまうのです。
「あの、わがまま娘が、とうとう男狂いをはじめた」
「逢うひと、逢うひと、みんな私を警戒いたします。もう、どこへも行きたくなくなりました。」
現代なら微笑ましい恋の始まりとして描かれるはずの行動が、当時の社会では“逸脱”と見なされる。
こうした背景を知らずに読むと、登場人物の感情や行動に共感しにくくなるのも無理はありません。
「わからなかった」は、文学への入り口
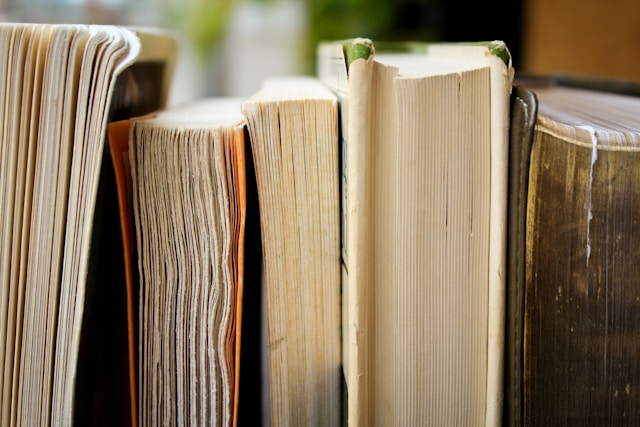
太宰の短編は、ストーリーや説明が極端に少なく、感情や余白で読ませるタイプの文学です。
その“わかりにくさ”にモヤモヤするのは、自然なこと。
けれど、そこにこそ人間の繊細さ、複雑さが凝縮されています。
登場人物の本心は語られず、行動に託され、読者がその裏にある感情を想像することで、物語が完成する。
太宰の小説は、読み手との“共同作業”で成り立つ作品なのです。
さいごに
「意味がわからなかった」読後感。
それは、あなたの読解力が足りないからではなく、「感じる余地」を持たされたからこその違和感かもしれません。
もう一度ページをめくってみてください。
最初は見えなかった感情の輪郭が、少しだけ浮かび上がってくるかもしれません。

