太宰治といえば、代表作『人間失格』や『斜陽』を通じて、「人間の弱さ」や「生きづらさ」を文学として昇華させた破滅と美を抱えた天才作家です。
そんな太宰にも、作家としての原点と呼べる、自伝的な初期作品が存在します。
それが、彼がまだ15歳のときに書いた『僕の幼時』です。
この作品は、同じ年に学校誌へ発表された『最後の太閤』よりも早く書かれており、あくまで個人的な作文として綴られたものでした。
わずか1000文字足らずの短文ながら、のちの太宰文学に通じる孤独、観察眼、家族との距離といったモチーフが凝縮されています。
『僕の幼時』の全文
僕は母から生れ落ちると直ぐ乳母につけられたのだそうだ。けれども僕はをしいかな其の乳母を物心地がついてからは一度も見た時もないし便りもない。物心地がついてからといふものは叔母にかゝつたものだ。叔母はよく夏の夜など蚊帳の中で添へ寝しながら昔話を知らせたものだ。僕はおとなしく叔母の出ない乳首をくはいながら聞いて居た。其の頃一番僕の面白かつたお話は舌切雀と金太郎であつた。こう言ふと僕はなんだかおとなしい子の様だが、実は手もあてられない程のワンパク者であつたのだ。一番僕にいづめられたのは末の姉様で、或時は折れたものほし竿で姉を追つて歩いたり、きたないわらじで姉のほゝをぶつたり、頭髪をはさみでちよきんと一つかみ位切つて見たりした。
其の度毎に姉は母様に訴ふるけれども母はなんともいはぬ。若しこのことが少しでも叔母の知る所となれば叔母はだまつては居ない。きびしくしかつて其の上土蔵に入れられたことも往々ある。そんな時には必ず小間使のたけが僕のかはりにあやまつて呉れる。たけは家の小間使でもあり、僕の家庭教師でもあるし、僕の家来でもあるのだ。五六歳の時から僕は毎晩/\たけの所に行つて本を教はつたものだ。始めはハタタコと一字々々に覚えて行くのは僕にとつてはたまらなく面白かつたのである。そして一、二ケ月の間にどうやら巻一は読める様になつた。学校に入いるによくなつた頃にはもう巻三にも手をのばし様になつた。うれしくてたまらないから叔母様に読んで見せると必ず昔話一つ知らせて呉れるし、おばあ様に読んで知らせればお菓子を呉れる。母様の前で読んでも何も呉れない。たゞ僕の頭をなでゝ一番とれよと云つて呉れる。姉様兄様に読んで見せてもたゞほめるばかりであつた。僕は昔話は大そう好きであつた。どんなに泣いて居る時でもどんなにおこつて居た時でも、昔話を知らせて呉れゝばすぐににこ/\するのであつた。だから僕は叔母に一番多く読んで見せたものだ。
僕の一番家でこはいものは父様であつた。故に父様の前では常に行儀よくして居た。それ程こはい父様でもたまには又大そう好きになることもある。それはよくぴか/\光つたおあしや、きれいな御本を呉れるからである。こうゆう風にして僕はずん/\成長して来たのだ。今でも叔母様やたけの事を思ふと恋ひしくてならない。
単なる「少年時代の作文」として片づけるには惜しい、すでに文学の芽が息づいている一作です。
この作品を深く理解すると、太宰の「感受性の高さ」はもはや褒め言葉では済まされず、彼の内面にあるどうしようもない複雑な感情に泣きたくなりました。
ついでに(いらないかもですが)私の感想もそっと置いておきました。
あらすじと登場人物

太宰治(当時は津島修治)は、青森県の大地主の家に生まれました。
裕福な家庭で育ちながらも、両親との関わりは薄く、乳母や小間使い、叔母といった「代替的な家族」と過ごす時間が多かったことが、この作品には淡々と描かれています。
乳母との別れ
生まれてすぐ乳母につけられた太宰ですが、物心つく前に彼女は家を去ります。
その突然の別れは、幼心に大きな喪失感を残しました。
叔母・きゑとの思い出
きゑは昔話を語ってくれる優しい存在でありながら、姉をいじめた太宰を土蔵に閉じ込めるなど、しつけも厳しく行いました。
太宰の本への興味を育てた存在でもあります。
小間使い・タケの存在
タケは読み書きを教え、太宰のいたずらの後始末までしてくれる存在で、まるで母親の代わりのような役割を果たしていました。
実の家族との距離
- 父:厳格で、ほとんど会話を交わすことがないが、金貨や豪華な本を贈ることで存在感を示す。
- 母:叱ることは少なく、「一番になれ」と抽象的な期待をかけてくる。
- 兄姉:本を読んだことは褒めてくれるが、深い心のつながりは感じられない。
- 祖母:音読のごほうびにお菓子をくれる、やさしい存在。
「観察者としての少年」──15歳の太宰が見つめた幼年期

この作品が驚異的なのは、15歳という年齢にもかかわらず、太宰がすでに自分自身の幼年期を「観察者」として冷静に描写している点です。
太宰の周囲の人々との関係や、幼い心に芽生えた違和感や寂しさが、淡々とした文章の中ににじみ出ています。
この時期からすでに、のちの太宰作品に通じるテーマ
- 他者との距離感
- 家族の中で感じる孤独
- 感情よりも観察が先に立つ視線
──が、すでにこの時点で芽生えていることに驚かされます。
わんぱくゆえに見えた、大人たちの距離と温度
太宰(=僕)は、姉に対して
「折れた物干し竿で追いかけ」
「わらじでほほをぶち」
「はさみで髪を切る」
という、もはや悪ガキを通り越したイタズラをします。
でも、そのあと姉が母に訴えても母は何も言わない。
しかし、叔母が知ると土蔵に入れられるほど厳しい。
この対比は、子どもながらに
「母はなぜ叱らないのか」
「叔母はなぜこんなに怒るのか」
といった大人たちの反応の差を敏感に感じ取っていたことを示しています。
愛情の“差”を描く観察力
また、本を読んで聞かせたときの家族の反応を比べてみましょう。
- おばあ様 → お菓子をくれる
- 叔母 → 昔話を語ってくれる
- 母 → ほめるだけで物はくれない
こういう「誰がどんな反応をくれるか」を逐一覚えていて、その違いをさりげなく書き分けているところに、子どもの目を借りた観察力と、家庭内の力学への関心が現れています。
これはもう、単なる「わんぱく坊やの日記」ではなく、家族という小さな社会の“構造”に対する目覚めです。
贈り物に込められた支配──幼き太宰と父の距離感
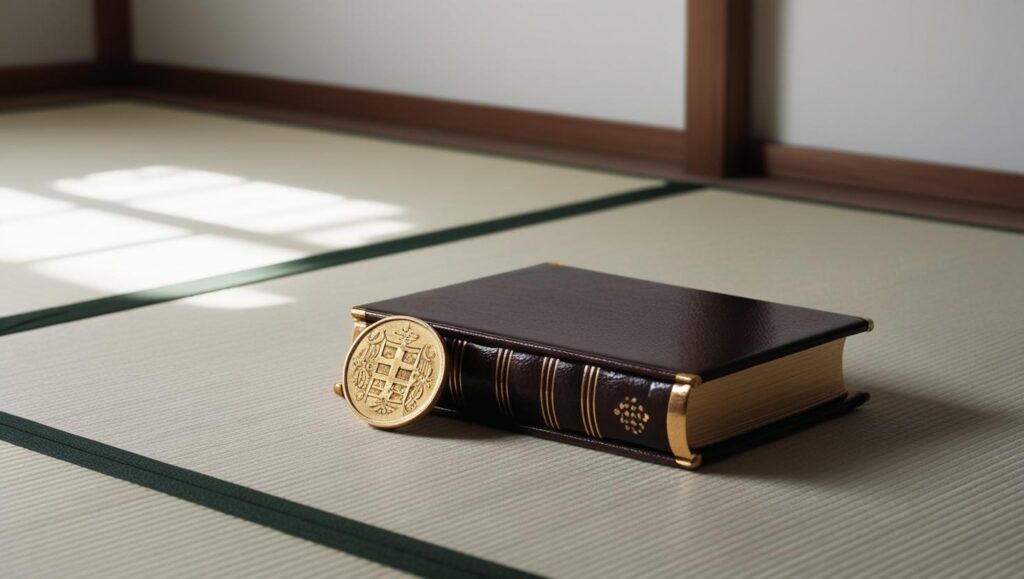
父親から贈られた「光ったおあし」と「きれいな御本」は、太宰の家庭環境と父との関係を象徴するアイテムです。
◆ 光ったおあし=物質的な力の象徴
「おあし」とはお金のこと。「光ったおあし」は金貨のような高価なもの。
父が経済的な影響力を持ち、それによって存在感を示していたことの表れです。
しかしその金銭的な贈り物は、温かさよりも“距離”を感じさせるものでした。
◆ きれいな御本=精神的な支配の象徴
「きれいな御本」は、装丁の美しい高価な本を指していると考えられます。
文化的で知的な贈り物である反面、「こうあるべき」という無言の圧力も含んでいます。
つまり、教育という名の支配。父の理想を無言で押しつけられていたとも言えます。
光ったおあし=物質的な力
きれいな御本=精神的な力
幼い太宰はその両方から影響を受けながらも、どこか冷ややかにそれを見つめています。
この二重の意味合いが、のちの作品『人間失格』などに見られる、金銭と芸術、家族と個人の葛藤へとつながっていくのです。
子どもらしからぬ観察眼と、父への複雑な感情
『僕の幼時』の核心は、後半に差しかかってからの父親に対する微妙な視線の描き方にあります。
幼年期の記憶という体裁をとりながらも、「父は威厳があった」だけで終わらず、父の振る舞いや距離感、子どもとしての自分の“困惑”や“観察”まで描いている。
これは単なる回想や美化ではなく、感情の複雑さや「わからなさ」をそのまま残す、太宰らしい感性が現れています。
「父を尊敬していた」ではなく、「父が“何か得体の知れないもの”に見えていた」ような、あの表現の揺れがすごく特徴的ですよね。
しかも本人はそれを「無自覚」に書いている。
つまり、計算ではなく生理的なレベルで空気の違和感を嗅ぎ取っている。
この“嗅覚”こそが、後の『斜陽』『人間失格』につながる文学の源だと思います。
この視点を軸に読み解いていくと、『僕の幼時』は決して「少年時代の作文」にとどまらず、すでに文学になりかけている作品として読めますね。
『僕の幼時』に見られる時代背景の影響

『僕の幼時』には、大正末期という時代の空気が色濃く反映されています。
家制度の影響
太宰は大地主の家に生まれましたが、当時の日本では「家」の存続が最優先。
親との距離が遠く、育児は乳母や小間使いが担うのが当たり前でした。
教育としつけの厳格さ
子どもは国家を支える存在として育てられ、しつけも厳格。
いたずらで土蔵に閉じ込められるなどの描写は、当時の常識を表しています。
家族のなかの「心の距離」
大正期の上流家庭では、「父は厳格で怖い存在」「母は感情を表に出さない」という空気感がありました。
『僕の幼時』でも「父が一番こわい」「母はただ頭をなでてくれるだけ」と描かれ、子どもが本音を出せる相手が限られている様子が見えます。
昔話の文化
「舌切雀」や「金太郎」など、夜に昔話を語り聞かせる習慣も登場し、テレビのない時代の家族時間が垣間見えます。
つまり『僕の幼時』には、「大正期の上流家庭に生まれた子どもが感じる孤独・甘え・反抗心」が、当時の家庭観・教育観・社会制度にしっかりと影響されて表れています。
普通の中学生には書けない、内省と観察の文体

私がもっとも驚いたのは、太宰の文体の“老成”ぶりです。
15歳とは思えないほど、冷静かつ内省的に家族や自分を描いているのです。
物心地がついてからといふものは叔母にかゝつたものだ。
「物心地がついてから」などの抽象表現や心理描写に文学的素養が見てとれて、年齢不相応な文体ですよね。
『僕の幼時』における太宰治(当時本名・津島修治)の冷静な観察力と、年齢不相応な文体や心理描写の背景には、彼の家庭環境と内面の成熟が深く関係していると考えられます。
「愛情の空白」が観察癖を育てた
乳母、叔母、小間使いと“母代わり”が何度も交替し、家族に対して「中に入る」のではなく、「外から見る」癖がついた。
感情を外に出せず、内面で処理
父親は政治家で威厳があり、母は病弱、兄姉は多く、末っ子の太宰は感情を出さずに「分析する」ことで自分を守っていた。
読書体験と文学的素養
漢文や古典を幼少期から読み、芥川龍之介や泉鏡花の作品に触れていたことで、「感情を言語化する力」が早くから身についていた。
「細密な描写」「心理の言語化」「言葉に対する感度の高さ」など文章で感情や記憶を整理する回路が若い頃ができていたのは、悲しいかな彼の境遇によるものだったんですね。
太宰の「家庭の違和感」に気づきはじめたきっかけの作品
『僕の幼時』は
今でも叔母様やたけの事を思ふと恋ひしくてならない。
という言葉で結ばれています。
母や父ではなく、叔母や小間使いのたけに対する深い愛着で終わっているのが印象的です。
太宰にとって本当の「居場所」は、血のつながった家族の中ではなく、むしろ“他人”に近い存在の中にあったのかもしれません。
このズレが、のちの太宰の作品に頻出する「疎外感」「居場所のなさ」「愛されなさ」へとつながっていくのだと思います。
太宰はこの作文の中で、子どものふりをしながら実は
━━家族とは何か、自分の愛着はどこにあるのか、人と人との関係の違い━━
をうっすら描き分けていた、とも言えるんですね。
短いながらも、家庭の力関係、愛情の在り方、教育、文学への入り口といったテーマがしっかり詰まっていて、太宰らしい観察眼と表現力の片鱗が見える作品です。
太宰治の原点が見える一編
『僕の幼時』は、ただの少年の思い出話ではありません。
太宰の「早すぎた孤独と成熟」が描かれています。
幼い心に宿った観察眼と内省癖、それを言葉にする能力──。
そのすべてが、のちの太宰文学へとつながる伏線なのです。
太宰ファンならずとも、この短い作品を通して「なぜ彼はあれほど人の心を描けたのか?」という問いの一端に触れることができるはずです。
私の感想
「ただ家族の状況を説明している」ように見えて、自分の家庭の“ズレ”や“特異さ”に無意識ながら敏感だった幼少期のころの太宰が読み取れる作品でした。
太宰の少年時代の文章には、自分の感情をどう扱っていいかわからないまま、それでも細部まで観察してしまう目の良さと、その観察がかえって自分を苦しめるような繊細さが同時にありました。
父親との距離を、「偉い人」「優しい人」ではなくて、「ちょっと怖い」「近づきがたい」「でも嫌いじゃない」といった矛盾した感情を、15歳の自分なりの言葉でどうにか書こうとしている。
それってもう、ただの「家族の作文」じゃなくて、感情を持て余した少年が、世界をどうにか理解しようとしている姿なんですよね。
読む側は、彼のその「割り切れなさ」にふれて、なんだか胸が詰まって、切なくなってしまう。
たぶん、「悲しくなる」って感覚は、太宰が読者の心の深いところに、
感情の“傷”や“ほつれ”のようなものを静かに触れてくるからなんだと思います。
こういう読後感を言葉にするのって、まさに太宰を読む醍醐味かもしれませんね。
